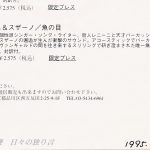A MOST PECULIAR MAN とても変わった人
彼はとても変わった人だった
リアドンおばさんが言っていた
おばさんはとても良く知っていた
彼女は彼の真上に住んでいた
とっても変わった人だと言っていた
彼はとっても変わった人だった
いつもたった一人で住んでいた
部屋に一人でこもって
自分自身の中に閉じこもって
とっても風変わりな男だった
友達もなく めったに口もきかなかった
彼に話しかける人もいなかった
親しみも見せずに 気にもしなかった
それに彼は誰とも違った人だった
彼はとっても変わった人だった
彼は先週の土曜に死んでしまった
彼はガス栓をひねって眠りについた
窓を閉めきって2度と目覚めなかった
彼の静かな世界へ旅立った
リアドンおばさんが言っていた
すぐ知らせなければならない兄弟が
どこかにいるはずだと言っていた
「死んでしまうなんて なんてことを」
みんな口をそろえて言っていた
( P.Simon / 対訳=乃木敏平)。・。・゜★・。・。☆・゜・。・゜。・。・゜★・。・。☆・゜・。。・。・゜★。・。・。☆・゜・。。・。・゜
Simon & Garfunkel – A Most Peculiar Man (Live Canadian TV, 1966)
本曲を、NHK-FM「サンセットパーク」(1998~2011)の前身にあたる東京発のFMリクエスト番組「夕べの広場」宛にリクエストし、番組でそのリクエスト曲が紹介された部分を、エアチェックしたカセットテープの音源から音声ファイルにしたものを下に埋め込みます。
NHK東京発FM「夕べの広場」(1993年11月25)
結局、サイモン&ガーファンクルの曲は番組でかからず、代わりに、直近にリクエストした、リアーヌ・フォリ―(1962~)の『だきしめてそして泣かせて』がかかっています。
Tear of Desire
私がリクエストカードに書いた文面に登場するギュスターヴ・モロー(1826~ 1898)は、19世紀末にフランスのパリに生きた画家で、外界から離れ、アトリエで大量の作品を描いています。
死後は、彼が暮らした家とアトリエをフランス政府が買い上げ、モローのための美術館にしています。
カードを読んでくださっているのは、当時、番組のパーソナリティをされていた日野直子さん(1937~)です。
私は上の歌詞を読み曲を聴くたびにイメージするのは、映画『タクシードライバー』(1976)に出てきた孤独な主人公・トラヴィス(Travis Bickle)の姿です。
Taxi Driver (2/8) Movie CLIP – I Gotta Get Organized (1976) HD
気になる投稿はありますか?
 夢うつつで聴いたピアソラ
気がつくと、うとうとと眠りかけていました。
そのとき私は、椅子に座り、イヤホンを耳の穴にはめ、デジタル・オーディオ・プレーヤー(DAP)のiPod classicで音楽を聴いていました。
そのとき聴いていたのは、アストル・ピアソラ(1921~1992)のアルバム"The Rough Dancer And The Cyclical […]
夢うつつで聴いたピアソラ
気がつくと、うとうとと眠りかけていました。
そのとき私は、椅子に座り、イヤホンを耳の穴にはめ、デジタル・オーディオ・プレーヤー(DAP)のiPod classicで音楽を聴いていました。
そのとき聴いていたのは、アストル・ピアソラ(1921~1992)のアルバム"The Rough Dancer And The Cyclical […] やっぱりいい音だったイヤホン
前回の本コーナーでは、別の目的でたまたま購入したイヤホンを実際に使てみたら、何の期待もしなかったイヤホンから、想像を超える良い音が聴こえてきて驚いたことを書きました。
https://indy-muti.com/49680/
その続編になります。
前回書いた中で、そのイヤホンの音が良く聴こえるのは、もしかしたら、私が使うタブレットPCのサウンド設計がそ […]
やっぱりいい音だったイヤホン
前回の本コーナーでは、別の目的でたまたま購入したイヤホンを実際に使てみたら、何の期待もしなかったイヤホンから、想像を超える良い音が聴こえてきて驚いたことを書きました。
https://indy-muti.com/49680/
その続編になります。
前回書いた中で、そのイヤホンの音が良く聴こえるのは、もしかしたら、私が使うタブレットPCのサウンド設計がそ […] 瓢箪から駒を感じさせたある物
「瓢箪から駒」という諺があります。あなたにはそんな経験がありますか? 私は昨日(27日)経験したばかりです。
きっかけは、このところ興味を持っているストップモーション・アニメーションです。
私はこれに興味を持ち、それが手軽に作れるStop Motion Studio […]
瓢箪から駒を感じさせたある物
「瓢箪から駒」という諺があります。あなたにはそんな経験がありますか? 私は昨日(27日)経験したばかりです。
きっかけは、このところ興味を持っているストップモーション・アニメーションです。
私はこれに興味を持ち、それが手軽に作れるStop Motion Studio […] Spotifyを介して私の今年を振り返れば
毎年同じように感じます。過ぎてしまえば、一年はあっという間という感じです。
今年も、今日を入れて残り九日を残すのみとなりました。とはいえ、私は年末年始には特別な思い入れを昔から持ちません。だから、大掃除のようなこともしません。
たまに障子張りをするぐらいですが、今年は面倒なので、これもしないことにします。
昔、何かで見たか聞いた話では、年末年始の時期には、 […]
Spotifyを介して私の今年を振り返れば
毎年同じように感じます。過ぎてしまえば、一年はあっという間という感じです。
今年も、今日を入れて残り九日を残すのみとなりました。とはいえ、私は年末年始には特別な思い入れを昔から持ちません。だから、大掃除のようなこともしません。
たまに障子張りをするぐらいですが、今年は面倒なので、これもしないことにします。
昔、何かで見たか聞いた話では、年末年始の時期には、 […]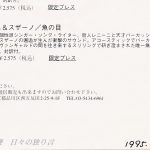 手元にある機材で愉しむ音楽
ここ数日、夕方になると好んで聴くアルバムがあります。"BRASILEIRAS"です。
私は購入したものに日付を残す癖があります。このアルバムには【1995.11.15】とあります。28年前のちょうど今頃手に入れたことがわかります。
CDアルバム『BRASILEIRAS』に記した購入した日付
CDアルバム『BRASILEIRAS』
アルバムのタイトルを […]
手元にある機材で愉しむ音楽
ここ数日、夕方になると好んで聴くアルバムがあります。"BRASILEIRAS"です。
私は購入したものに日付を残す癖があります。このアルバムには【1995.11.15】とあります。28年前のちょうど今頃手に入れたことがわかります。
CDアルバム『BRASILEIRAS』に記した購入した日付
CDアルバム『BRASILEIRAS』
アルバムのタイトルを […]