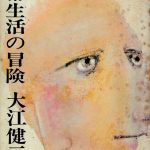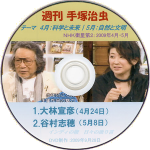昔、NHKで放送されたバラエティ番組の1コーナーに「減点ファミリー」があったのを記憶する人がいるでしょうか?
私はコーナー名をよく憶えておらず、「満点パパ」だったかな? と思ってネットで検索し、それが「減点パパ」(1973年4月)で、そのあと「減点ファミリー」(1975年4月13日に改称)になったことを知りました。
そのコーナーは、週末のゴールデンタイムにNHK総合で放送されていた「お笑いオンステージ」(1972年4月8日~1982年4月4日)の中にあったコーナーです。
私も見た記憶があります。コーナーのMCは三波伸介(初代)(1930~1982)です。
毎回、有名人がゲストとして招かれますが、招かれるのは当人ばかりではありません。コーナーにははじめ、有名人の子供たちだけが登場します。
三波も、どの有名人の子供なのか知らずに接していたのか、それとも知った上で、知らないふりをして接していたのかはわかりません。
三波は子供たちに、父親のことを訊きます。その様子を見る視聴者は、それを見ながら、この子供たちの父親は誰なのか、それぞれに連想する仕掛けです。
三波は絵を描くのが得意で、子供たちから訊きだした特徴を絵に描き、彼ら彼女らのお父さんの似顔絵を仕上げます。そのあとに、当人が登場し、子供たちを交えて家族の話をする趣向です。
こんな番組があったのを思い出させてくれたのは、阿刀田高(1935~)が書いた『頭は帽子のためじゃない』です。この本については、少し前に本コーナーで取り上げました。
この電子書籍版が、思いがけず利用できるようになったAmazonのKindle Unlimitedに該当していたため、無料で読むことができました。
阿刀田がそのときどきに考えたことや起きたことなどについて書いたコラムを一冊に収録する体裁となっています。
その中に、「往復ビンタ」と小見出しのついたコラムがあり、その中に、阿刀田が「減点ファミリー」に出演した時の思い出が書かれています。
『頭は帽子のためじゃない』が紙の本で出版されたのは昭和63年1月10日とあります。平成が始まるのが翌年1月8日ですから、実質的には、昭和最後の年にあたります。
阿刀田には、男・女・男の順で子供がおり、番組には下のふたりが出演したそうです。娘が小学6年生、息子が4年生のときのことです。
番組作りの裏話のようなことも書かれており、収録が始まる前に、番組のプロデューサーが子供たちに会い、話をしながら、面白そうな質問を作り、その質問に沿って、三波が番組内で子供たちに質問したそうです。
その質問は子供たちのお父さんには知られないようにしてあります。収録が始まってから、子供たちに質問し、その答えを父親に連想させたりするためです。
下の息子には、「これだけはお父さんには止めて欲しいこと」が質問となったようです。
お父さんの阿刀田には想像がつかず、「オナラかな?」などと答え、そんなこといわなければよかった、とあとで考えたりしたそうです。
今、こんな答えだったら、テレビのバラエティ番組の1コーナーとはいえ、今よりも波風が立ったかもしれません。
息子の答えが、父親にされる「往復ビンタ」だったからです。
息子が三波から「もう少しくわしく説明してください」といわれ、ポーズをしながら次のように答えます。
半歩足を開いて、手を腰にあてろ、そういってから殴るんです。
阿刀田は番組で、体罰を是認するようなことを述べたこともあって、反響が大きくなり、雑誌や新聞からの取材が多く、「いささか弱り切っている」と書いています。
この番組について書いたコラムの後半は、阿刀田の子供時代の体験に費やされています。
ほかのコラムにもありますが、幼い頃の阿刀田は引っ込み思案のところがあり、学校に通い始めたはじめの年は、家族に連れられて学校へ行くものの、校舎には入らず、家に戻ってしまったりした、というようなことです。
阿刀田の父は、子供の阿刀田を殴ることは一度もなかったそうです。気が弱かった子供時代の阿刀田はいじめっ子の格好の標的で、誰かに殴られることに免疫がなく、学校のガキ大将に殴られそうになると、怖くて怖くて仕方がなかったそうです。
別のコラムには、いじめっ子らに解剖ごっこをされたようなことが書かれています。それがどんないじめだったかわかりませんが、あとあとまで阿刀田を悩ませた可能性もあります。
そうした原体験を持つ阿刀田は、自分の息子たちには殴られることに免疫をつけようと、敢えて手を上げた、といった面があります。
殴るといっても、決して、感情に任せて殴ることはしなかったそうです。悪いことは悪いのだと幼いうちからはっきりわからせるため、理性を持って殴ることを自分に課したようです。
そのため、「手を腰にあてろ。半歩足を開け」と宣言するセレモニーを経たのち、殴ったそうです。
そうであっても、今同じことをいう人がテレビの番組に登場すれば、波風が立たずに済むようには思えません。
阿刀田の本書によって、昔に流行った歌が思い出されました。こちらは、「男らしさ」という小題のコラムに書かれています。
その歌は、吉田拓郎(1946~)が作詞して、かまやつひろし(1939~2017)が歌った『我が良き友よ』(1975)です。「はやったのは昭和五十年代の初め頃だったろうか」と阿刀田が書いています。
その歌詞にある次の一節を耳にするたび、気になって仕方がなかった、と書いています。
その歌詞は次のようなものです。
男らしさはやさしいことだと言っとくれ
問題は、「やさしいこと」をどのように受け止めるか、です。
私ははじめから阿刀田が受け取った意味で受け取っていました。それでも、多くの人は、「男らしい男になるのは、それほど難しいことではない」の意味に採っているのでしょうか?
阿刀田が考え、私も同じように考えた、「男らしさというのは、男が持つやさしさのことじゃないのか」という意味です。
ただ、阿刀田はどこまでもこだわるたちで、「男のやさしさ」といっても、若い女性のいう「やさしさ」が、阿刀田の考える「やさしさ」と同じものかどうかを疑うようなことを書いています。
今の男女にもその傾向が窺えます。
たとえば、彼女の誕生日を忘れずにいて、誕生日になると必ず、お祝いの電話をかけてくるのが「男のやさしさ」とされてはいないか? と。
阿刀田は、そのような「やさしい男」は「マメな男」というだけで、男の本当のやさしさは、もっとクールであるべきだ、と書いています。
たとえば、男に年頃の娘がいたら、娘が本当に幸福になるにはどういうことを考えたらいいか、一番深いところに根差す配慮をする。そんなことが、父親の娘に対する「やさしさ」というものだろう、といようなことを書いています。
そのコラムの結びには、阿刀田が読んだばかりだというロシアの詩人、アレクサンドル・プーシキン(1799~1837)の伝記にあった逸話を紹介しています。
プーシキンは、自分の妻にいい寄った男に決闘を申し込み、その決闘で負った傷がもとで死んでいます。そのプーシキンが、妻に次のような言葉を残したというのです。
「気にするな。お前は悪くないんだ。みんなオレのしたことなんだ。だれからも忘れられるように田舎へ行け。そして二年間だけ喪服を着てくれ。その後は再婚……今後はもっとましな男を選ぶんだな」
阿刀田 高. 頭は帽子のためじゃない (角川文庫) (Kindle の位置No.2004-2005). 角川書店. Kindle 版.