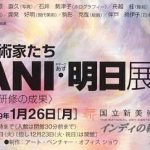前回の本コーナーでは、村上春樹(1949~)のエッセイ集『職業としての小説家』(2015)に書かれている、村上の小説執筆工程について書きました。
それを書きながら、絵画の制作過程でも同じような話が書けそうなことに気がつきました。
ここでは古典的な欧州絵画を想定した話になります。
それを大ざっぱに分類すれば、細部まで克明に描かれた絵画と、細部が大ざっぱに描かれた絵画に分けることができます。そして、それぞれの制作過程は、大きくふたつに分かれざるを得ません。
精密に描かれた絵画として私がイメージするのは、油絵具を初めて本格的に使用した画家のひとりとされるヤン・ファン・エイク(1395~1441)の作品です。エイクがたとえば宝石を描けば、写真よりも細密に描かれているように感じます。
このような絵画を描く場合は、下絵を正確に描くことから始まります。この下絵の出来栄えが、最終的な出来栄えに直結します。
一方、細部が大ざっぱに描かれた絵画で私がイメージするのは、私が最も敬愛する17世紀のオランダの画家、レンブラント(1606~1669)です。
レンブラントも、修業時代は細部まで丁寧に描くようなことをしています。しかし、親方のもとを離れ、独立して仕事をする中で、独自の表現を獲得しています。
その末に手に入れた制作方法によって、今日称えられるレンブラントのレンブラントたる作風を獲得します。
レンブラントの後期の作品は、細部だけを拡大してみると、抽象絵画のように見えます。絵具が好き勝手にカンヴァスに塗りつけられたようになっているからです。
このような描き方を、エイクのような細密絵画では決してしません。
レンブラントの後期の作品は、近づくとそのように見える部分が、離れてみると、これ以上ないほど、本物らしく見えます。同じような描法は、スペインの宮廷画家、ベラスケス(1599~1660)の絵画でも見ることができます。
レンブラントやベラスケスは、ほとんど下絵は書かなかったものと思います。メディウムで薄く溶いた絵具を使い、直にカンヴァスに形をとり、それを修正しつつ、絵具をのせていきます。
ここまで、絵画の制作方法について書きました。
村上は、それがどんな長編になる小説であっても、あらかじめプロットを作るようなことをしていません。これは、下絵をまったく描かずに、いきなり絵具で描き出すレンブラント後期の描き方に共通するように感じました。
自分で絵を描いて楽しいのは、いきなり描き出すレンブラントのような描き方です。下絵を描いた上に色をつけるのでは、塗り絵をしているような気分になり、色をつけるのが苦痛になります。
十年以上前、もしかしたら二十年ぐらい前、私が速乾性のアクリル絵具を使って絵を描く様子を動画にして、本サイトで紹介しました。その描き方が、レンブラントの制作方法を自分なりに考えたものでした。
NHK-FMのリクエスト番組「夕べのひととき」や「夕べの広場」、のちの「サンセットパーク」(1998~2011)に宛てたリクエストカードには、この描き方で描いたイラストを添えました。
同じような絵画の制作過程を、また、ビデオカメラで撮影して、本サイトに載せることをしても面白そうです。
小説家の中には、原稿用紙やワードプロセッサーで書き出す前に、しっかりとした土台を作る小説家もいるでしょう。その書き方であれば、結末がわかった上で書くことになり、筋が大きく破綻する恐れはありません。
しかし、それは「障害」にもなり、書いている途中で別のアイデアがひらめいても、新たな展開は盛り込みにくくなります。
人間ですから、あとになって、前に考えたよりも良いアイデアが浮かぶことがあります。そんな場合も、「下絵」通りに話を進めなければならないとしたら、可能性の芽を自分で摘んでいるのと同じことになりはしないでしょうか。
村上の長編小説に『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013)があります。
この作品についてもエッセイ集に書かれています。村上は、原稿用紙にして60枚ぐらいの短編小説にするつもりで書き出したそうです。
東京で仕事をする多崎つくるに、二歳年上の木元沙羅という恋人ができます。つくるが、高校時代に親しくしていた四人の親友から、理由もわからず、突然、絶交されたことを話すと、沙羅から次のようにいわれます。
(あなたは)自分が見たいものを見るのではなく、見なくてはならないものを見るのよ
村上春樹. 職業としての小説家(新潮文庫) (p.195). 新潮社. Kindle 版.
小説の登場人物は、小説家が頭の中で作った人物で、話す言葉も小説家が考えたものです。そうであるのに、村上は沙羅の言葉を文字にしながら、それまで考えていなかったことを沙羅からいわれたように、衝撃を受けます。
小説を書く人は、人物がしっかり描けていれば、あとはその人物に任せるだけで、話は自然に前へ進んでいってくれる、というようなことをいいます。
村上は、自分が作りだした沙羅の指摘に心を動かされ、自分でも想像していなかった話に展開していき、その果てに、フィンランドまで行くようなことになります。
そのことは、それを書いている村上自身に「とっても大きな驚きでした」との感想を持たせています。
こうしたことは、プロットを基に書く小説家には起こりえないことでしょう。
読者が望むのは、綺麗に整えられた予定調和の話ではなく、次に何が起こるか、書いている小説家にも予測できないような、想像を超えた展開です。
私の場合は、本コーナーに文章を書くだけですが、どんな展開になるかわからないまま書き出すのが好きです。あらかじめプロットのようなものを作ろうとは思いません。
そのように書き出す村上ですが、途中からは、細密画を描く画家のように、とことんまで書き直す作業をしていることを知りました。
写真と見紛(みまが)うようなリアルな絵画を称賛する人がいますが、私は、そのような絵画であれば、写真で済ませばいいように感じ、特別それが素晴らしいとは思いません。
村上の場合は、自分が書く作品を完璧なものにするため、何度も書き直す作業をするのでしょう。その結果、書いた村上が納得するのはいいのですが、第三者がその作品に接することを考えると、そればかりが正解ではないように思います。
写真のように描かれた絵画に感心する人と、感心しない人の二種類の鑑賞者が絵画の場合にはいます。同じことが、文字によって表現される小説の読者でもいえるのではないか、と考えるからです。
レンブラントが人生の後期に描いた作品は、細部だけを近づいて見れば、未完成のように見えます。それこそが、私には素晴らしく思えるのです。
同じようなことが、小説の場合はどうなるのか、具体的に書くことはできませんが、それに通じるような、あいまいな部分を残すことで、作品の中に余白のようなものを敢えて作り、それが読む人に、知らず知らずのうちに作用するようなことはないでしょうか。
ほんの思いつきで書きました。ですので、確信のようなものはありません。なんとなくそんな感じがしただけのことです。
そんな感じで読んでもらえたら助かります。