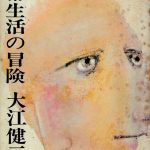本日の朝日新聞に、平山周吉氏(1952~)が執筆した『小津安二郎』(新潮社)が、第50回「大佛次郎賞」を受賞することを伝える記事が載っています。
本賞は、優れた散文作品を顕彰する賞で、朝日新聞社が主催だそうです。
それにしても、映画監督・小津安二郎(1903~1963)の評伝を書いた人が、平山周吉というのは出来過ぎです。
小津の代表作『東京物語』(1953)で、笠智衆(1904~1993)が演じる主人公の名が平山周吉だからです。小津はほかの後期作品でも、「周吉」の名を何度か使用しています。
このたび大佛次郎賞を受賞された平山氏は、文藝春秋社で長年編集の仕事をされ、その後、独立して文筆家になられたそうです。
そして、独立する際に、大好きだという小津にちなみ、『東京物語』の主人公の名を筆名に選ばれたのだそうです。
ともあれ、平山周吉氏はこの受賞に対し、「小津安二郎の特別な記念の年だから、下駄を履かせていただいたのかな」と謙遜されています。
その小津の生誕120年を記念する今年の12月は、小津の誕生日と命日が12日だったこともあり、NHK BSとBS松竹東急で、立て続けに八作品が放送となりました。
私は特別小津に詳しいわけでもないのですが、今回の特集にお付き合いし、これまで、八作品中六作品を本コーナーで取り上げました。
今回は、昨日、NHK BSで放送されて見たばかりの『お早よう』(1959)について書きます。
それにしても、タイトルだけを見たら、どんな話になるのか想像がつきにくいでしょう。私は以前に見たことがあり、昨日再び見ながら、そうだ、こんな話だったと思い出しました。
タイトルの『お早よう』ですが、なぜ『お早う』にしなかったのか、気にならないでもありません。
タイトルも含めた文字について書けば、後期の小津作品を見る限り、白黒の作品もカラーの作品も、いつも同じスタイルで表示されます。
油絵を描くためのカンヴァスで、地塗りがされていない、麻の布地がそのままのようなものを背景にして、作品タイトルや制作スタッフ、出演者が、毎回同じ活字で表示されます。
小津は『彼岸花』(1958)から遺作の『秋刀魚の味』(1962)までの六作品をカラーで撮っています。
カラー作品のタイトルにも、小津なりの工夫といいますか、遊びが垣間見えます。
白黒作品のときは、文字が白一色でした。それがカラー作品では、名前の一文字だけなどが赤にされています。なんでも、赤が小津の好みの色だったそうです。
カラーといえば、本作を見て、小津がカラー作品の撮影のために選んだアグファ(現在のアグフア・ゲバルト)が持つ色味が感じられました。
本コーナーで前回取り上げた『小早川家の秋』(1961)は、本作の二年後に公開されています。松竹映画を代表する小津が、『小早川家の秋』を宝塚映画(宝塚映像)で制作し、東宝系で公開したこともあるのか、東宝系映画に共通する色の表現に感じ、特別、小津のアグファカラーには感じませんでした。
それが本作は、見始めたときから、独特の色味を個人的に感じました。
小津は、アグファのフィルムが、小津の好む赤の発色をよくするから選んだとしています。しかし、本作を見ると、彩度の高い鮮やかな赤ではありません。
彩度を敢えて下げた、渋みのある赤に見えます。一口に赤といっても、赤という色はさまざまな色味を含有します。本作に見られるような「赤」が小津の好みで、それを出せるアグファのフィルムでなければならなかったということでしょう。
舞台は東京郊外の多摩川沿いの高い土手の下に広がる新興住宅地です。すべてが平屋で、いい方は悪いですが、マッチ箱のような小さな家が、隣家とくっつくように立ち並んでいます。
通勤する大人も、通学する子供たちも、高い土手の上を歩いて向かいます。
家々の間から高い土手が見える構図を小津は好んでよく使っています。家々の間から見える高い土手の上に、人が立っていたり、人が歩いて、現れては消える姿が小さく見えます。
そのような構図の映像を見て、私はひとりの写真家を思い浮かべました。
生まれ育った鳥取にある鳥取砂丘などで、人の配置をデザインした写真を撮った植田正治(1913~2000)です。演出した植田の表現は、「植田調」といわれます。
同じことを、小津は動く映像でしているように感じます。
本作について書かれたネットの事典ウィキペディアを読んで、驚いたことがあります。それは、本作が短期間で作られたことです。
本作が公開されたのは1959年5月12日ですが、ロケーションハンティング(ロケハン)は同年の1月だそうです。そして、撮影は2月27日から4月19日です。
撮影が終わって、一カ月経たないうちに公開されています。
当時はテレビ放送が始まっていますが、テレビを持つ家はまだ多くなかったでしょうか。本作でも、主人公の家にはまだテレビがなく、その家の中学生と小学生の兄弟は、テレビがある近くの家に行ってテレビを見てばかりしているとして、両親に叱られます。
テレビ番組の代わりを担ていたのが映画という側面がまだ残り、今のテレビ番組を作る感覚で、映画が量産された側面を感じます。
今書いた本作の主人公の家には、笠智衆(1904~1993)が演じる定年を数年後に控えた会社員・林敬太郎と妻の民子、中学生の実と小学生の勇がいます。
民子を演じたのは、後期小津作品の常連といえる三宅邦子(1916~1992)です。三宅も小津のお気に入りの俳優のひとりといえましょう。
三宅は、小津の『戸田家の兄弟』(1941)で、戸田家の長男の妻を演じたのを皮切りに、遺作の『秋刀魚の味』まで、後期小津作品に、いずれも主だった役で九作品に出演しています。
本作では、三宅が演じる妻の民子の出演シーンが多くあります。描かれる多くが、家庭を預かる主婦の目線で描かれるからです。
今は、結婚しても夫婦が共働きをする家庭がおそらくほとんどとなり、専業主婦はきわめて珍しい存在になったといえるのではないでしょうか。
本作が作られた当時は、専業主婦が世の主流で、時間を持て余していたわけでもないでしょうが、同じ住宅地に肩を寄せ合うように暮らす女性陣は、顔を合わせては、噂話に余念がありません。
本作にも杉村春子(1906~1997)が出演しています。強く印象に残るのは、杉村が演じる、きく江の母の、みつ江です。
いろいろな意味で「存在感」があるからです。
みつ江を演じているのは三好栄子(1894~1963)です。三好についてウィキペディアに次のように特徴が書かれています。
ギョロ目と大きな口が特徴の性格女優として活躍
この表現では足りないほどの「存在感」が三好にはあります。三好は小津の『東京暮色』(1957)で産婦人科の女医を演じ、その時初めて三好を見た私に印象が強く残りました。
三好は、小津が亡くなった年の7月末に亡くなっています。老衰で亡くなったというのですが、享年は69です。今の次代よりも老化が早かったのでしょうか。
朝の通勤通学時間、住宅地の住人が利用する鉄道の駅のホームで、佐田啓二(1926~1964)が演じる福井平一郎と、久我美子(1931~)が演じる民子の妹、節子が、バッタリ出会うシーンがあります。
佐田啓二は、中井貴一(1961~)の父親であることはご存知でしょうか? 本作に出演した時佐田は33歳で、その年頃の中井の姿がだぶります。
それはともかく、平一郎と節子は、「お早う」「お早う」と挨拶を交わし、電車が到着するまでの間、ふたりで空を見上げては、浮かんでいる雲が何かの形に見える、などと、取り立てての意味のない会話をします。
これは、本作のタイトルの「お早よう」につながるように思います。
意味のないように思える言葉のやり取りが人と人との生活には満ちている。それが世の中を回す潤滑油となり、人々の何でもない日常が平滑に回っていく。というような意味になりましょうか。
ラストシーンは、青空を背景に、物干しざおに干された男子中学生のパンツです。
そのシーンを書くことで、本作が持つ雰囲気がわかってもらえたでしょうか?
ここまで、本コーナーは後期小津作品を見ては、順に取り上げてきました。残すところは、来週火曜日(26日)にNHK BSで放送予定の『秋刀魚の味』のみとなりました。
おそらくはそれを見た、来週水曜日(27日)に本コーナーの更新をすることになりそうです。