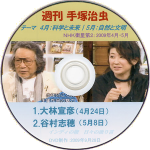年度替わりで、私がよく見聴きしているテレビやラジオ(AM・FM)でも、出演者が新しい人に交代ということも珍しくありません。
今日、新年度になって初めての放送となった「新日曜美術館」(日曜美術館)の司会も、この4月からアシスタントの女性が、前年度までの写真家・織作峰子さん(1960~)から、新しい人へと替わりました。
確か、作曲家と紹介されていたように記憶していますが、確信を持てません。あとで確認して、間違っていましたら訂正しておきますね(作曲家で間違いありませんでした)。男性の司会者はこれまで通り石澤典夫アナウンサー(1952~)です。
新年度最初の番組で取り上げたのは、岸田劉生(1891~1929)です。
彼の名前は、もしかしたら一度はお聞きになったことがあるかもしれません。そう。あの一連の「麗子像」を描いたことでも知られる画家です。
彼が画家として歩み始めた時代、日本では白樺派と呼ばれる団体(運動?)があり、彼らはその当時の西洋絵画の最も新しい動きであった印象派絵画を積極的に日本に知らしめ、多くの専門家に影響を与えていたようです。
そして、当然であるように、劉生もその影響を受けることになります。
ただ、本日の番組を見ていて面白いと思ったのは、ゲストで出演されていた作家で演出家の久世光彦氏(1935~2006)が、白樺派について次のように発言されたことです。
私は常々白樺派というのは(日本の主に洋画に与えた影響という意味では)諸悪の根元ではないかと思っています。
これまで美術番組を見ていて、白樺派を賛美することはあっても、このような率直な指摘は耳にしたことがありませんでした。放送メディアを通しては、今回初めて聞きました。それを聞いた私はといえば「確かに、久世さんのいっていることはあながち的外れではないかも」と我が意を得たりの気分になったのです。
そうなんですよね。日本に初めて紹介された西洋絵画が印象派だったため、それ以前の脈々と培われた西洋絵画の伝統である写実絵画はある意味蔑ろにされ、結果的に、日本で油彩絵画といえば印象派風の絵画ばかりになってしまいました。
もしも、印象派だけではなく、それまでの伝統絵画も平等に紹介されていたなら、日本のその後の油彩はどのような道を歩んで行ったのか興味があります。
それはともかく、はじめは白樺派に影響を受けた劉生でありましたが、久世氏も指摘されていたように、劉生は印象派絵画に納得できなくなり、それ以前の伝統的な絵画へと嗜好が移って行くことになります。
その後、運命的ともいえるモデルが誕生しました。娘の麗子の誕生です。
以後、劉生は娘をモデルに、ヨーロッパの古典的絵画の代表ともいえるアルブレヒト・デューラー(1471~1528)を思わせるような重厚な肖像画を描くようになりました。かくして一連の麗子像の始まりです。
ところで、劉生は近代日本絵画の代表画家のようにいわれますが、一般の人は彼の作品を見てどのように感じるものなのでしょうか。
またしても久世氏ですが、彼が育った家にあったという折れ曲がった階段の突き当たりの壁には麗子像(複製画?)が掛けられていたそうで、3、4歳の頃から見るともなしに劉生の絵には接していたそうです。
久世氏の麗子像の感想はといえば、「気持ちの悪い絵ですね、あれは」です(いい方はこの通りではありません。ただ、ニュアンスはこんな感じでした)。
久世氏が子供の頃のある夕暮れ。雷鳴が轟き、家中の電気が消えました。ちょうど例の階段にさしかかっていた久世少年は、薄暗い階段の途中で、稲妻の青白い光によって照らし出された麗子像を目にします。
作家でもある久世氏の作り話、ではないとは思いますが、シチュエーションとしてはこれ以上はないと思えるほどの絶妙な場面設定によってあの絵を鑑賞したことになります。以来、劉生のというよりも、描かれた麗子の姿が不気味さと共に氏の脳裏に強烈に焼きついてしまっているようです。
「在るという事の不思議さよ」とは劉生が記した言葉です。
劉生は見たまま、見えたままを描くと同時に、そこに存在することの不思議さをも表現しようと試みます。しかし、「在る」とはどういうことか。劉生は悩みます。そして、そうした思いを日記に面々と書き綴りました。
劉生がたどり着いたのは次のような考えです。
デロリとした感覚
人間が一個の生物として生きているということは、普段は意識していないかもしれませんが、実はとてもグロテスクなことである、というわけです。そして、それを1枚の絵の中に表現しようとします。
劉生は東京の銀座に生まれ育ったそうです。彼は子供の頃からいたずら好きだったのか、ある時次のようないたずらをしたのだそうです。
彼は「血まみれの小指」を本物そっくりに造り、人通りの多い銀座の通りに置きました。そして、それを発見しては驚いて立ち止まる人々の姿を遠巻きに眺めてはひとり楽しんだのだそうです。
このエピソードは、その後の劉生の作品世界にも通じるような要素を含んでいるように思えないこともありません。
ここで、私自身の劉生の作品に対しての個人的な感想を率直に書けば、やはり古臭さのようなものを正直いって感じてしまいます。
それは、それよりも遙か以前の時代のレンブラント(1606~1669)(私が最も敬愛するオランダの画家)の作品などからは決して感じることのない古臭さです。
あるいは、その辺が日本における西洋絵画の「限界」であるように思えないこともありません。
いずれにしても、専門のモデルを使うことなく、我が娘をモデルに作品を描いた劉生は、その点に置いては自分自身に誠実な画家であったといえると思います。
劉生は四十の声を聞くことなくこの世を去っています。享年は(私個人が「天才の定義」の要素のひとつとしている「夭折(ようせつ:年が若くて死ぬこと=広辞苑)」のタイムリミット直前の)38です。