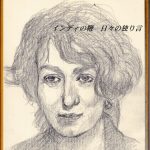昨日の続きで、映画『タクシー・ドライバー』について書いていこうと思います。
作品の内容については、本コーナーで以前に書いたものやネットの関連サイトを参照していただくことにしまして、本日は、昨日仕上げたDVDの中で監督のマーティン・スコセッシが語る制作の裏側に話の焦点を絞ることにします。
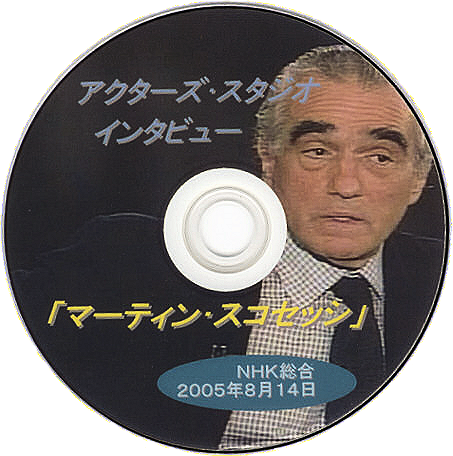
この作品の脚本を担当したのはポール・シュレイダーです。といって、初めに監督のスコセッシに作品のイメージがあり、それをシュレイダーに脚本を頼んだのではありません。逆です。
当時、スコセッシはブライアン・デ・パルマと交流があり、彼から、シュレイダーが『タクシー・ドライバー』という脚本を書いて持っていると教えられます。
その出来が素晴らしいらしいということで、スコセッシは早速接触を試みますが、初めはまったく相手にされないばかりか、「つまらない男」と煙たがられたといいます。それでも粘り強く交渉を続け、ようやく映画化のOKサインをもらいます。
スコセッシは今でこそ押しも押されもしない巨匠ですが、この作品を撮っていた頃はまだ認められていなかったのか、ほとんどノーギャラだったという話には驚かされました。「アクターズ・スタジオ・インタビュー」のインタビューアーを務めるジェームズ・リプトンにその点を訪ねられたスコセッシは、「金なんて、もらったかな?」とおどけて答えました。
まじめな話、映画作りに夢中になっていて、金儲け云々は二の次、三の次だったそうです。ギャラの話題にオチをつけるように、「今度の仕事にはギャラが出るぞ」といわれたときのエピソードを披露するスコセッシでした。
この作品で重要な位置を占める、バーナード・ハーマン作曲の音楽についても触れないわけにはいきません。
私は個人的にこの作品のテーマ音楽がたまらなく好きで、長年聴き続けているNHK-FMのリクエスト番組「サンセットパーク」へも、何度もリクエストしているほどです。
その名曲が生まれる背景について、スコセッシは興味深い裏話を披露してくれています。
スコセッシが作品を作る際、ハリウッド的な音楽を使うことは避けたといいます。代わりにスコセッシが考えたのは、彼自身が親しんできた音楽を使うことです。それをBGMにしようということです。
しかしその考えは、『タクシー・ドライバー』の主人公であるトラヴィスを考えれば、変更せざるを得なくなるのでした。
なぜなら、トラヴィスは、スコセッシ曰く「復讐の天使」なのであり、人々が日常的に聴くラジオから流れてくるような音楽には親しんでいないはずです。それでは、映画のバックに流れる音楽としてはふさわしくありません。
そこで次にスコセッシは、バーナード・ハーマンに音楽を依頼することが考えます。自分の作品に、トラヴィスにぴったりの音楽を作ってもらおうというわけです。
しかし、この話もすんなりとは運びません。ロンドンにいるハーマンに電話でその話をもちかけたスコセッシに対し、「そんなものはやらん!」とまったく取り合ってもらえなかったたそうです。
そんなハーマンの態度を変えさせたのもトラヴィスのキャラクターです。ロンドンに飛んだスコセッシから手渡された脚本に目を通したハーマンは、主人公の特異なキャラクターに興味を示し、「(作品に力強さを持たせるために)金管楽器だけでいこう」と彼の方から提案をしてきたそうです。
かくして、作曲人生の最後に『タクシー・ドライバー』を作曲したハーマンは、作曲作業終了直後のクリスマス・イヴに息を引き取りました。
「空想と現実とが同居する世界の住人のトラヴィス」を象徴的に描いているのが、有名な鏡の前での一人芝居です。が、驚いたことに、そのシーン、脚本には「トラヴィス 鏡を見る」とだけ書かれていたといいます。ということで、トラヴィスを演じたロバート・デ・ニーロによる即興の演技だったことが監督によって明かされました。
その場面、スコセッシは鏡の前に立つトラヴィスに何か語らせようとは考えていましたが、撮影のスケジュールが押していたこともあり、とりあえずデ・ニーロに何か即興でしゃべるよう指示を出します。それを受け、デ・ニーロは「おれに用か?」と演技をして見せます。
スコセッシは「それだ!」と感じ、「そのまま続けろ」と指示を出し、そうして撮影されたフィルムを編集したトム・ロルフの的確さとも相まってあの名シーンは誕生したのでした。
ここまで書いてきて、私はまったく別のテレビ番組を思い出し、何とかトラヴィスの話につなげられないかと考え始めています。
それは、本サイトの自己満足コーナー(←全部自己満足なんじゃないのぉ(^O^;?)「私のTV指定席」先週の火曜日分にも載せてあります「知るを楽しむ」(NHK教育)の12月火曜日「私のこだわり人物伝・幻影城へようこそ 江戸川乱歩」です。
全4回シリーズの第1回目。ナビゲーターを務める大槻ケンヂさんは、「イケナイものを見てしまった」という表題で、江戸川乱歩の代表作である『屋根裏の散歩者』について語っています。ついでまでに、私はその復刻本を持っていたりします(^_^;
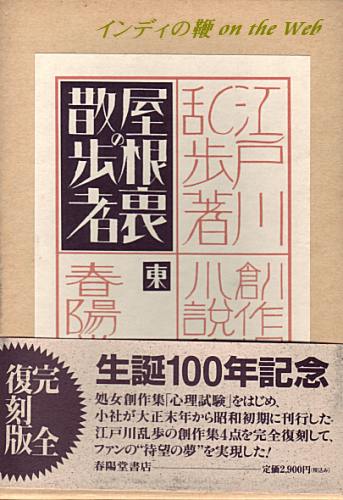
その中で私がなるほどと思ったのは、小説の主人公である郷田三郎を「ニート、フリーター、引きこもりの元祖」と定義していることです。
もちろん、乱歩が生きた時代、そんないい方はなかったわけですが、いわれてみれば、なるほどと思えます。
大槻さんは郷田三郎という人物を次のように分析します。
主人公の三郎は、社会のルールに乗っていないがゆえに、世間一般の常識の中で生きることを善しとしている人間とは異なる視点で世の中を見ることができた 。
そうしたタイプの人間については、他でもない私自身がソレに限りなく近いキャラクターであるため、本サイトでもことあるごとに書いてきたつもりです。
大槻さんの指摘を借りれば、そうした社会から逸脱してしまっているような人間でも、社会との関わりを持ちたい渇望はあるものなのであり、郷田三郎には、それが犯罪という形で現れたのでした。
トラヴィスもラストで血生臭い銃撃戦を繰り広げますが、彼はヒーローの扱いを受けます。