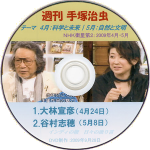「つじむら・じゅさぶろう」という人物がいます。この人物がどのような人で、どのようなことをされているか、ご存じでありましょうか。
個人的には、以前から「つじむら」さんには関心を持ち、テレビで「つじむら」さんが取り上げたりしますと、かなりマメにチェックしてきたように思います。
「つじむら・じゅさぶろう」。以前は「辻村ジュサブロー」。今は「辻村寿三郎」(1933~2023)と書きます。職業は「人形作家」です。
その昔、NHKで『新八犬伝』(1973~1975)という人形劇が放送になり、人気を博しました。その劇に登場した400体ほどにものぼる人形のほとんどすべてを作ったのが辻村ジュサブローで、辻村寿三郎さんです。
その辻村さんを取り上げる番組が今、放送中です。番組は、NHK教育の教養番組「知るを楽しむ・人生の歩き方」(月曜~木曜|午後10:25~10:50|2005~2010)です。この番組では曜日ごとに異なるラインナップを揃え、今月の水曜日「人生の歩き方」では、辻村さんを取り上げた「辻村寿三郎・人形が教えてくれた」が4回シリーズで放送中です。
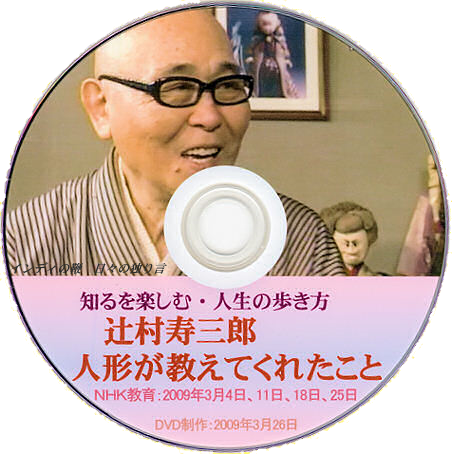
その第1回目「“美”の魔力に捕らわれて」(3月4日)を見て、感じるところが多々ありましたので、本日はそのことについて書いてみようと思ったわけです。
辻村さんは一貫して人形制作に人生のすべてを捧げていらっしゃいますが、何か物を作る人間には、「独特の匂い」があるように思います。辻村さんからもその匂いが強く感じられます。それもあって、昔から気になる存在でもあったのでしょう。
昭和8(1933)年のお生まれということで、今年で76歳になられることになるわけですが、私が辻村さんを知るようになって以降、辻村さんといえばいつも着物をお召しになっています。そして、この着物の存在が、今に続く辻村寿三郎という人形作家を支えていることを知りました。
生まれたのは、今も書きましたように、昭和8年。日本が先の大戦に突入していく8年前ということになります。生まれた場所は、辻村さんのお言葉をお借りすれば「幻の国」満州国、中国大陸の東北部です。
そこへ日本から移り住んだ両親の下に生まれていますが、どんな事情があったのか、生後すぐに辻村家に養子(ようし:養子縁組によって子となった者=広辞苑)として入ったそうです。養父は鉱山技師、養母は芸者を何人も抱える料亭の女将(おかみ:料理屋・旅館などの女主人=広辞苑)でした。養父は、寿三郎さんが5歳の時に他界したそうです。
「三つ子の魂百まで(幼い時の性質は老年まで変わらない=広辞苑)」といいますが、これは寿三郎さんに濃密に反映されているといわざるを得ません。
母親と一緒に写った寿三郎少年の写真が番組でも紹介されましたが、そこに写る寿三郎少年は、決して快活(かいかつ:はきはきとして元気のあること。明るくさっぱりして勢いのよいこと=広辞苑)そうな子供には見えません。引っ込み思案そうで、神経質そうでもあります。
これは、寿三郎さんが持って生まれた性質というものでしょう。
それに拍車をかけたのが、寿三郎少年の育った環境です。少年は母子とふたりの家庭です。また、母親が女将として芸者たちを何人も使っているため、少年の周りにはいつでも着物を着た女性たちがいました。
いつの頃からか、寿三郎少年はあるモノに強い執着心を持つようになります。芸者たちが身につける着物です。もっといえば、着物の布地そのモノです。少年は、芸者たちが脱ぎ捨てた着物を、目を盗んで手に取ったりもしたでしょうか。少年はその布地の肌触りや柄に強烈に惹きつけられていきます。
その傾向は日増しに強まり、自分を押さえきれなくなったのでしょう。少年は、お座敷に着ていく着物にハサミを入れるまでになってしまいます。どうしても欲しくなった布地の柄を、寿三郎少年はハサミで切り取って自分のモノにしてしまったのです。
そんなことがたびたびあったと番組で語っていました。ちなみに、今回の聞き役は、NHKアナウンサーの葛西聖司氏(1951~)です。
その寿三郎少年の布へのこだわりは、ある種「病的」な段階にまで達していたのでしょうか。養母は、養父亡き後、ひとりで我が子とした寿三郎さんを育てていましたが、子の行く末を案じるようになっていきます。
寿三郎さんが少年時代を過ごした旧満州という土地柄も、寿三郎さんが生み出す人形に強い影響を与えていることを知りました。当時の満州では、街角で京劇が催されたそうです。それを寿三郎少年は、あの一途そうな眼でじっと見つめたことでしょう。
当時の思い出を尋ねられた寿三郎さんは、見てきたばかりのことのように、当時の話をしました。それを語る寿三郎さんは、スキンヘッドです。また、左耳だけにイヤリングをしています。手振りや身振りを交えて熱っぽく語る寿三郎さんの口調には、どこか女性的なものを感じないでもありません。
京劇を演じる女優が、衣装の入った引き出しを引いた場面をまるで昨日のことのように話す寿三郎さんです。引き出しの中には、髪につけるかんざしがあり、引き出された振動でそれが揺れ、カワセミの羽で作ったというかんざしが光にキラキラッと輝いたのでしょうか。それを見た寿三郎少年は「ファ~」っとした気持ちになり、堪らなくなったそうです。
そういえば、寿三郎さんが『新八犬伝』の人形でも見せたような人形の顔つきは、メイクをした京劇の俳優たちに通じるように思います。結局のところ、何もないところから生み出されたような絵でも人形でも、土台となるものは、その人間がそれまでに見てきたモノの中にある、ということなのでしょう。
日本が戦争状態になり、戦局がいよいよ悪化した昭和19(1944)年、養母は寿三郎少年を連れて日本に帰ってきます。帰ったのは、養母の生まれ故郷という広島県の三次(みよし)というところで、寿三郎さんは母親が亡くなる20歳までその地で過ごしています。
日本に帰ってきてからも、養母の心配の種は寿三郎さんでした。養母は、寿三郎さんを「何とか普通の男の子」にするため、寿三郎さんに手に職をつけさせようと奮闘します。が、当の寿三郎さんは、当時から自分の興味の対象以外には一切関心が向かわなかったそうです。
その頃から、寿三郎さんは人形を作るような職業に就きたいと考えていたそうです。きっかけは、山口の「小萩(こはぎ)人形」だそうです。これは、布の切れ端を使って作られた小さな人形です。時代が変わり、それまで武家の奥様だったような女性も、生活に困るようになります。それで、持っていた高価な着物を売ってお金に換えたりもしたのでしょう。
そうした着物の切れ端を使い、小さな人形を作り、幸せだった頃の自分の縁(よすが:手がかり=広辞苑)にしたのでもありましょうか。その人形に惹かれた寿三郎少年は、人形作りを先生に教えてもらおうとしますが、「男の子は教えられない」とでもいわれて断られたのか、先生に習った近所のおばさんにこっそり習ったりしたようです。
この「小萩人形」作りは、幼い頃から執着してきた布とも合体します。あの手触りと柄。その布地を活かして人形を作ることこそが自分の天職と思ったことでしょう。しかし、当時、人形作家という職業などあるはずもなく、自分を活かす職業に就くこともできず、悶々とした日々を過ごしたようです。
旧制中学時代に演劇部を作った寿三郎さんは、養母の置きみやげのような「あれは名優だよ」という言葉に刺激され、養母の四十九日も済まないうちに、広島の三次を離れ、前進座を旗揚げした河原崎国太郎(5代目)を頼り、上京します。これ以降のことにつきましては、寿三郎さんの番組が終了した時点で、また取り上げることがあるかもしれません。
以上、本日は、現在放送中の「知るを楽しむ・人生の歩き方」から、人形作家・辻村寿三郎についてのあれこれを書いてみました。
個人的には、当たり前な人間の当たり前の人生には興味が向かいません。その点、幼い頃から「普通の男の子」でなかった辻村寿三郎という人間には、様々な角度から興味が尽きません。
異常に布地というものに魅せられ、結局、それをこれ以上ないほどに活かす仕事に就けた辻村寿三郎さんは、間違いなく幸せな生き方をされていることになります。