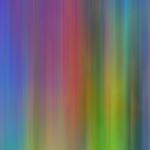該当するAmazon電子書籍版に、高ポイントがつくキャンペーンのとき、読んでいない村上春樹(1949~)の作品が多くがそれに含まれていることを知り、12冊まとめ買いしました。そのあと別に3冊追加し、15作品を出版順に読んでは、本コーナーで感想を書いています。
このところは、とんとんとんと読み進み、村上の長編小説『スプートニクの恋人』(1999)を読み終え、次の『アフターダーク』(2004)にとりかかったところです。
| 作品名 | 出版社 | 出版年月日 |
|---|---|---|
| 風の歌を聴け | 講談社 | 1979年7月23日 |
| 1973年のピンボール | 講談社 | 1980年6月17日 |
| 羊をめぐる冒険 | 講談社 | 1982年10月13日 |
| カンガルー日和 | 平凡社 | 1983年9月9日 |
| ノルウェイの森 | 講談社 | 1987年9月4日 |
| ダンス・ダンス・ダンス | 講談社 | 1988年10月13日 |
| 遠い太鼓 | 講談社 | 1990年6月25日 |
| 国境の南、太陽の西 | 講談社 | 1992年10月5日 |
| やがて哀しき外国語 | 講談社 | 1994年2月18日 |
| アンダーグラウンド | 講談社 | 1997年3月20日 |
| 辺境・近境 | 新潮社 | 1998年4月23日 |
| スプートニクの恋人 | 講談社 | 1999年4月20日 |
| アフターダーク | 講談社 | 2004年9月7日 |
| 東京奇譚集 | 新潮社 | 2005年9月18日 |
| 小澤征爾さんと、音楽について話をする | 新潮社 | 2011年11月30日 |
残る作品は、読み始めた小説を加えて3作品になります。先が見えてきました。
今回取り上げる『スプートニクの恋人』というタイトルを聞き、ロシアがソビエト連邦といわれていた時代に同国が展開して衛星打ち上げの「スプートニク計画」を重ねることができる人は、歳がいった人か、その方面に関心を持つ人でしょう。
私は特別詳しいわけではなく、例によってネットの事典「ウィキペディア」を頼りとします。それによれば、スプートニク1号が打ち上げられたのは1957年だそうです。本作が出版されたのは1999年ですから、その時でさえ、1号の打ち上げが47年経っています。
1999年といえば、私が初めてPCを使い始めた年です。今に続く本サイトの原型を作って公開を始めたのもこの年になります。今のWordPressに切り替えるまでは、テキストエディタを使い、手書きでHTMLファイルにして公開しました。
メカに弱いと書く村上ですが、それにしてはPCに接するようになるのが早く、1992年頃からマッキントッシュ製のPCを使っています。村上は、PCのワードプロセッサ(ワープロ)で小説を書く用途があって早くから使い始めたのでしょうけれど。
スプートニク2号では、雌犬を乗せて打ち上げています。衛星が地球に戻ることはなく、何も知らない犬は宇宙空間を漂い、息絶えるしかありませんでした。おそらくは、犬の立場になって想像した村上は、本作に「スプートニク」とつけざるを得なかった(?)のでしょう。
本作の前までに発表された村上の作品は、私が知る限り、主人公の「僕」の視点で描かれた一人称だけが用いられました。本作では、主人公は「僕」から「ぼく」に換えています。理由はわかりません。
全編にわたって「ぼく」で始まる文章が並びますが、次の一カ所だけは「僕」になっています。
彼女は美しく、行動力があり、優しかった。僕の好みからすれば、いささか化粧が濃かったが、服装の趣味はよかった。
村上春樹. スプートニクの恋人 (講談社文庫) (Kindle の位置No.1320-1321). 講談社. Kindle 版.
他はすべて「ぼく」です。この「僕」は意図したものか、それとも、PCのワープロで書いた村上の変換間違いでしょうか。印刷に入る前に校正が入るのだと思いますが、そこでも、もしかしたら見落とされたのかもしれません。
同じようなケースをもう一カ所見つけました。次の記述です。
家を囲む低い石壁には赤いブーゲンビリアの花や鮮やかに咲き乱れている。
村上春樹. スプートニクの恋人 (講談社文庫) (Kindle の位置No.1636-1637). 講談社. Kindle 版.
村上は、「赤いブーゲンビリアの花や」ではなく、「赤いブーゲンビリアの花が」と書いたつもりではなかったでしょうか。
読み始めた『アフターダーク』は、村上がずっと採って来た一人称の表現を離れ、三人称で書かれています。また、本作においても、「ぼく」が大学時代に出会い、付き合いのつづく「すみれ」の視点による一人称や、三人称で描かれる場面もあります。
この時期の村上は、自分の表現の幅を広げるつもりがあったのか、それとも、別の意図で、表現方法を模索していたのかもしれません。
本作に登場する人物は限られます。主人公の「ぼく」のほかには、「すみれ」と「すみれ」が同性でありながら思いを寄せる39歳の女性の「ミュウ」と「ぼく」が性欲を満たすために付き合うガールフレンドぐらいです。
村上の作品は性描写がよく登場します。それが苦手で、村上作品を敬遠する向きもあるでしょう。本作にもそれは登場しますが、『国境の南、太陽の西』などと比べると、その要素は薄まっています。
村上作品でもうひとつ特徴的なのは、現実と想像の境があいまいなことです。本作でも、主要人物3人が、そのようなものを見ます。
ミュウは25歳のときまで、プロのピアニストを目指していました。フランスへ留学していたミュウは、その年の夏、フランス国境に近いスイスの小さな町へ行き、そこが気に入り、しばらく滞在します。
あることで精神的に追い詰められたミュウは、ある夜、自分が暮らすアマートの窓から見える遊園地の観覧車に乗ります。営業の終了間際に無理をいって乗せてもらった観覧車は、ミュウだけを乗せて、暮れなずむ町の空を回転します。

ミュウは持っていた双眼鏡で、アパートの自分の部屋を覗きます。すると、そこに信じられない情景を目撃します。
覚めた目で読めば、ミュウが幻覚を見ているようにしか思えません。ほかのふたりが見たものにしても、同じように考えるのが現実的です。もっとも、それで片付けたら、小説は成り立たなくなりますが。
本作以前の村上の小説は、書いている村上も結末を知らずにいるように思われます。あるところで、構想を立てずに書き始める、と書かれていたように記憶します。
本作では、大きな骨組みを組んでから書き始めたような気がします。本当のところはわかりませんけれど。
人は誰でも、宇宙空間を移動する衛星のように、たったひとりで生きていくしかありません。誰とも交わらなければ、宇宙空間に放り出されたのと同じように、絶対孤独です。スプートニク2号に乗せられて宇宙空間に打ち上げられた雌犬のように。
衛星になぞらえた個人は、あるときは他の衛星と短い時間交わって飛行するように、他の誰かと時間を共にします。しかし、いつまでもその衛星と同じ軌道を辿ることはできず、やがてバラバラになり、再び出会う可能性は限りなく低くなります。
そんな構想が頭に浮かんで書き出したすれば、結末を知った上で書き始めたであろう、と私は想像します。
雌犬を乗せたスプートニク2号はその後どうなったでしょうか。その衛星を見つけたというニュースを私は知りません。