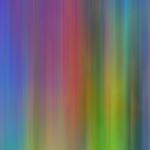このところは「シリーズもの」のように、村上春樹(1949~)の作品を本コーナーで取り上げています。それ以前にも、村上の作品を読んだあとに取り上げることをしていますが、今回は、3回続けて村上作品です。
いずれも、Amazonの電子書籍版で読んでいまして、今回は、米国に移り住んだときに書かれた随筆集『やがて哀しき外国語』(1994)です。
村上の長編小説は、村上作品が持つ独特ともいえる性描写に辟易させられることが多いですが、それが随筆であれば、まさか、米国滞在中に経験した性的な経験をあからさまに書かない限り、そうした描写は出てきません。
もちろん、米国人の女性と村上が実際に交わったことがあるかどうかはわかりませんが、そんな逸話は一切登場しませんので、その点では気楽に読めます。
本作は、1991年の1月末に、米国の大学から客員研究員に迎えられたことで、約2年半を大学のある周辺に夫人と暮らす間、講談社のPR誌『本』に連載した随筆がもとになっています。
それ以前、村上は3年間、南ヨーロッパに滞在し、その時のことをまとめた『遠い太鼓』(1990)を読み、本コーナーで取り上げたばかりです。
そちらは、イタリアのローマを起点としながら、南ヨーロッパを中心にギリシャの島々に小旅行したことなどが書かれており、原稿の分量は本書よりも多くなっています。
本書は、約2年半に起きたことをそのまま書くというのではなく、日本から離れて暮らす中で、村上が感じたり考えたことがまとめられています。ですから、米国に暮らしながら、日本のことなども登場します。
すでに書いたように、『遠い太鼓』に比べて文章の量が少ないため、一日程度で読み終わりました。
本書を読むことで、それまで知らなかったことを思いがけず知ることができました。もしかしたら、ネットの事典「ウィキペディア」にも記述されていない(?)こともあるかもしれないです。
そのひとつは、私にとっては軽い謎であった、村上の陽子夫人の実像がわかったことがあります。
たしか、二人は大学在学中に結婚し、その後の人生を共にされています。二人の間には子供がなく、それだからか、どこへ行くのにも、そして外国へ長期間住むときも必ず夫人を同伴します。
そんな夫人はどういう肩書なのか、個人的には気になっていました。
私の疑問を解く文章が、「元気な女の人たちについての考察」にありました。
米国人と知り合い、世間話をするようになると、十中八九訊かれる質問のひとつに「村上の奥さんは何をしているのか?」です。米国の事情がわかるまでは、村上を戸惑わせた質問になります。
この問いかけに対し、隠し立てするつもりがなかったであろう村上は、「いえ、何もしていません。ただのハウスワイフです」と答えたといいます。実際問題、対社会的に、夫人が何かをしていたわけではないからです。
それを読みながら私は、「そうか。陽子夫人は何もせず、創作活動をする村上のまわりに存在するだけなのか」と納得しました。そうはいっても、毎日の食事を作ったり、家の掃除などをするでしょうから、専業主婦といったところになるでしょう。
今は共働きする夫婦が増え、専業主婦は減っているかもしれません。しかし、今から30年ほど前のことですから、陽子夫人が専業主婦であっても、何ら不思議ではありません。なんせ、村上は売れっ子作家で、村上の稼ぎだけで十分すぎる暮らしができたでしょうから。
ところが、米国人はその答えに納得しません。村上の顔を見る相手の顔がこわばって見えたそうです。そのような顔をする相手の心内には「それだけじゃないだろう?まだ他に何かやっているだろう?」という思いが見え隠れします。相手が米国人の女性であれば、自立していない女性と見て、釈然としないらしいです。
そんな経験経たことで、村上は次のように付け足すことを覚えます。
「(前略)彼女は僕の個人的な編集者兼秘書のような仕事をしています。僕の書いた文章を読んでチェックし、それについて感想を述べ、整理します。電話に出て(僕はまず電話には出ないので)、手紙の返事を書きます。アメリカでも同種の仕事をこなさなくてはならないので、学校に通って英語を勉強しています」
村上春樹. やがて哀しき外国語 (講談社文庫) (Kindle の位置No.1590-1592). 講談社. Kindle 版.
この部分を読んで、村上に関することで二つのことを知りました。ひとつが、個人的に謎(?)だった夫人の役割です。ただの専業主婦だと思っていた夫人が、実は村上のマネージャーのようなことをしており、対外的な交渉役のようなことをしているであろうことです。
そして個人的には驚いたのが、夫人が村上の個人的な編集者のようなことまで受け持っているらしいことです。しかし、それを知ることで合点できたことがあります。
前回の本コーナーでは、村上の長編作品『太陽の西、国境の南』(1992)を取り上げました。
これは、米国に移住して、1年ほどで書き上げたそうですが、書き上げたばかりの作品を読んだ夫人が、「盛り込まれた要素が多すぎる」と注文を出し、それに従った村上は、大胆なことに、『太陽の西、国境の南』と、次の長編作品になる『ねじまき鳥クロニクル』(第1部 第2部 1994|第3部 1995)に分割したというのです。
そのエピソードを読み、ずいぶんと夫人の意見に従順に従ったものだな、と感心しました。夫人が村上の個人的編集者のような立場であれば、わからないわけではありません。
ただ、それを知ったことで、別の疑問を持たないでもありません。夫人がどの程度の権限を持つか知りませんが、その力が大きすぎる場合、別の問題が出てきそうな気がするからです。
出版社には専属の編集者がいるはずです。本来であれば、社の編集者がすべての権限を持つところ、その間に、自分以上の権限を持つ人がいたら、さぞかしやりづらかろう、という想像ができます。
『太陽の西、国境の南』のAmazonにあったクチコミの中に、夫人は村上作品の中でこの作品が一番好きと書かれてあるのを見つけました。夫人が、村上の妻の立場を離れ、客観的な編集者の眼で見てそう考えるのなら、「そうなのか」と納得しますが、そこに少しでも贔屓目があるのであれば、多少厳しいいい方を承知でいえば、自分の夫の作品の編集者的仕事をするのは控えた方がいいのでは、と思わないでもありません。
小説は、出版社を経由して、多くの読者に届けられるものです。小説はそれを書いた小説家のもので、何を書いても許されるものかもしれません。しかし、一方で、社会的な責任のようなものも負わされています。であるからには、出来上がった作品を厳密に吟味する責任を、担当の編集者はプロ意識によって持たなければなりません。
そして、プロの編集者の眼で見て、「これは世に出すべきではない」と判断すれば、たとえ自分が担当する作家の作品であっても、自分の責任において、ボツにするぐらいのこともときには必要でしょう。
それだけの覚悟が、村上の夫人にないとはいえませんが、身内であるゆえの甘さがあるとしたら、何度も書いて申し訳ありませんが、マネージメントに専念し、編集は専門の人に任せた方がいいように感じます。
余計なお世話であることを知りながら、思いついたことを書きました。
もうひとつ、村上が電話を苦手にしていることも、初めてぐらいに知りました。本書は30年ぐらい前に書いたことで、今は電話に出るようになっているのかもしれません。それでも、電話に出ないことが続いたのであれば、どこで生活するにしても、職業柄、体外的な交渉事は必要になり、夫人はいなくては困りましょう。
村上夫妻は、1989年10月に、3年間のヨーロッパ滞在から日本に戻り、そのあとまた、数カ月、英国で暮らしています。その時は確か、村上が独りで生活することをしていたはずです。その時のことも、『遠い太鼓』に書かれていましたが、そのときは、誰とも口をきかず、部屋に籠って作品を書いていた、とありました。
家に籠らなけらばならない状況が、あることによって引き起こされたことを、本書を読むことで知りました。
それが書かれているのは「運動靴をはいて床屋へいこう」です。
この項目の「文庫本 付記」に、実はということで、今は日本に住んでいるときも、ユニセックスの美容院に行くようになったと書いていますが、それまでは、日本に暮らしていたときは、住むところが変わっても、東京都内某所にある床屋で15年くらい、髪形を整えてもらっていたそうです。
村上は、髪形にはこだわりがまるでなく、いつも行く床屋で椅子に座るだけで、いつも決まったように髪の毛を短くしてもらい、髪の毛に整髪料のたぐいはつけず、床屋で整えられた髪形でどこへでも出かけていたそうです。
それが、外国で長い期間暮らすようになると、床屋へ行くことで難題を抱えることになったそうです。村上の思い通りの床屋が外国では見つからなかったからです。私が村上の立場であっても、同じように難問に感じたでしょう。
もっとも、私の場合は、床屋へも、ましてや美容院などというところへ絶対に行きません。嫌いだからです。それでも、髪の毛は伸びます。私は鏡を見て、髪が伸びたと思ったら自分で短くするだけです。ですから、その点では、どこに住んでいても、床屋で困ることはありません。
私も長いこと、髪は短くするだけで、整髪料のたぐいはまったく使っていませんでした。それが、10年近く前から(だったかな?)からは、それを使って、自分なりに髪形を整えるようになりました。とはいっても、まったくの自己流で、他人にはどう見えるかわかりませんが。
そんな事情を抱える村上が英国のロンドンに滞在していたとき、ある床屋を見つけ、目をつぶるように飛び込み、えらい目に遭た話があります。
村上を担当した理髪師の男は、自慢げに口上を述べ始めます。彼は村上に「君はラッキーなヤツだ」といい、「日本人には日本人に向いたヘアカットがある。でも、ここは日本じゃない。だから、ここにいつ奴に、そんなカットができる者はいやしない。それが俺にはできる。そんな俺に巡り合ったのだから、君はラッキーというわけだ」と。
男が口上で述べたのとは裏腹に、村上は無茶苦茶な髪形にされてしまった(←村上の感想)のでした。
村上は、鏡に映る自分の髪型を凝視することもできなかったそうです。他人に自分の惨めな髪形を見られるのを極度に嫌い、しばらく家から出ずに過ごしたそうです。そうしたこともあって、家に籠って作品の執筆に励んだ、という裏の事情が窺えました。
「ブルックス・ブラザースからパワーブックまで」では、村上の執筆環境を知ることができます。
1986年秋からヨーロッパ滞在を始めた村上ですが、『ノルウェイの森』(1987)は、それまでの執筆環境で、大学ノートやレターペーパーに、水性ボールペンや万年筆で書いています。それが、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)を書く頃までには、ワードプロセッサー(ワープロ)に変わっていたことを『遠い太鼓』を読んだことで知りました。
そして本作では、ワープロも卒業し、おそらくは普及し始めたばかりのPCのワープロ機能を使って書くように変わったことが知れます。
村上が選んだのはマッキントッシュ製PCで、はじめに手に入れたのは“PowerBook 160/80”で、当時の米ドルで2200ドルとあります。しかも、同じPCを日本で買ったら倍近くになるのでは、とも書き添えています。以来、現在に至るまで、マックのPCで創作活動を続けているそうです。
YouTubeで同機種の動画を捜して知りましたが、同機が発売されたのが1992年ですから、村上は出てすぐのPCを米国で手に入れ、使い始めたことになりそうです。私が使うPCはWindows製ですが、使い始めたのは、村上に遅れること7年です。
村上はメカに強くないと書いていますが、それにしては、最先端のメカに接するのが早いです。PCに関しても、私は村上の7年後輩です。
ともあれ、紙に書いていた頃は、仕上げた原稿が失われる恐怖を常に抱え、街で消防自動車を見かけると、もしや、自分の住まいが火事で焼け落ち、自分の原稿が消失してしまったのでは、と悪い想像をしたりしたそうです。それが、ワープロやPCで執筆するようになったことで、そうした不安は解消されるところとなりました。
まだ読んでいない村上作品は6作品あります。
| 作品名 | 出版社 | 出版年月日 |
|---|---|---|
| 風の歌を聴け | 講談社 | 1979年7月23日 |
| 1973年のピンボール | 講談社 | 1980年6月17日 |
| 羊をめぐる冒険 | 講談社 | 1982年10月13日 |
| カンガルー日和 | 平凡社 | 1983年9月9日 |
| ノルウェイの森 | 講談社 | 1987年9月4日 |
| ダンス・ダンス・ダンス | 講談社 | 1988年10月13日 |
| 遠い太鼓 | 講談社 | 1990年6月25日 |
| 国境の南、太陽の西 | 講談社 | 1992年10月5日 |
| やがて哀しき外国語 | 講談社 | 1994年2月18日 |
| アンダーグラウンド | 講談社 | 1997年3月20日 |
| 辺境・近境 | 新潮社 | 1998年4月23日 |
| スプートニクの恋人 | 講談社 | 1999年4月20日 |
| アフターダーク | 講談社 | 2004年9月7日 |
| 東京奇譚集 | 新潮社 | 2005年9月18日 |
| 小澤征爾さんと、音楽について話をする | 新潮社 | 2011年11月30日 |
次は、日本に戻っていた村上が、1995年3月20日月曜日の朝に起きたオウム真理教による「地下鉄サリン事件」の被害者に、村上が直接話を訊いてまとめた『アンダーグラウンド』(1997)を読む順番になります。
そうした本を出すことになろうとは、ともしかしたら村上自身が驚いた(?)かもしれません。