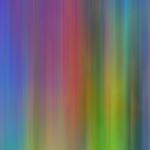ポイントが125(定価の20%)つくことに惹かれ、村上春樹(1949~)の短編集『回転木馬のデッド・ヒート』(1985)をAmazonの電子書籍版で読みました。文学作品を読む動機としては不純でしょう(?)か。
どんな短編集かは、読み始めるまで知りませんでした。
村上は、1979年に文芸雑誌の『群像』に応募した『風の歌を聴け』(1979)が群像新人文学賞を受賞し、それがきっかけで、作家デビューしています。
たしか、その年だったか、神宮球場の芝生の外野に寝転んで野球観戦しているとき、ふと、小説を書いてみようかと思い立った、と当時を振り返って書いたエッセイで読んだ記憶があります。
誰にとっても人生は成行です。そのときに村上が応募した作品が選ばれず、彼が別の人生を歩むことになっても、それが彼の人生です。小説を書くことばかりが人生ではありません。
ネットの事典ウィキペディアで本短編集のあらましを調べると、元々は、『IN★POCKET』という文芸PR誌(当時は隔月刊)に連載されたもののようです。
その雑誌の編集者は、村上が『群像』で文学新人賞を取ったときに編集を担当した人で、その人が『IN★POCKET』に担当が変り、村上に執筆を依頼して連載が始まっています。
連載順に書くと次のようになります。
| プールサイド | 『IN★POCKET』1983年10月号 |
| 雨やどり | 〃12月号 |
| タクシーに乗った男 | 〃1984年2月号 |
| 今は亡き王女のための | 〃4月号 |
| 野球場 | 〃6月号 |
| 嘔吐1979 | 〃10月号 |
| ハンティング・ナイフ | 〃12月号 |
短編集にまとめるにあたり、前書きの意味で『はじめに・回転木馬のデッド・ヒート』と『レーダーホーゼン』を書下ろしています。
書下ろしの『レーダーホーゼン』は、長年連れ添った妻が、ドイツへのひとり旅で、夫に頼まれたレーダーホーゼンを買いにある街を訪れ、それがきっかけで、夫と娘を棄てることになる話です。
短編集では発表順ではなく、『はじめに・回転木馬のデッド・ヒート』『レーダーホーゼン』『タクシーに乗った男』『プールサイド』『今は亡き王女のための』『嘔吐1979』『雨やどり』『野球場』『ハンティング・ナイフ』の並びです。
『はじめに・回転木馬のデッド・ヒート』で、これらの短編集は、村上が誰かから聴いて面白いと思った話を、発表するあてもなく書き、他の断片的文章と同じで、光を浴びずに終わる運命を辿る予定のはずだったようです。
しかし、三つ四つと話がたまり、それらが何かしら通じ合う意味を有するように感じるようになります。その感覚を村上は、「(誰かに)話してもらいたがっている」と書いています。
私は村上の作品をそれほど読んでいませんが、これまで読んだ中では、性的なことを書くことが多い印象です。なぜそうなのか、理由はわかりません。
本短編集でも、セックスに絡む話がいくつもあります。
『雨やどり』では、金で自分の体を5度売ったことがあると話す女が村上の話し相手です。彼女の話を聴く村上は、金で女を買ったことは一度もなく、今後もないだろうと書きます。
この短編の結びは次のようになっています。
そして僕はその昔、セックスが山火事みたいに無料だったころのことを思い出した。本当にそれは、山火事みたいに無料だったのだ。
村上春樹. 回転木馬のデッド・ヒート (講談社文庫) (Kindle の位置No.1573-1574). 講談社. Kindle 版.
同じ短編の中で、自分たちにとってセックスとは何か、次のように書いています。
しかし年をとり、それなりに成熟するに従って、我々は人生全般に対してもっと別の見方をするようになる。つまり我々の存在あるいは実在は様々な種類の側面をかきあつめて成立しているのではなく、あくまで分離不可能な総体なのだ、という見方である。つまり我々が働いて収入を得たり、好きな本を読んだり、選挙の投票をしたり、ナイターを見に行ったり、女と寝たりするそれぞれの作業はひとつひとつが独立して機能しているわけではなく、結局は同じひとつのものが違った名称で呼ばれているにすぎないということなのである。
村上春樹. 回転木馬のデッド・ヒート (講談社文庫) (Kindle の位置No.1337-1342). 講談社. Kindle 版.
これは村上が若かった頃の考えです。今も変わっていないのかわかりません。また、この考え方が正しいかどうかもわかりません。
ともあれ、その頃の村上は、好きな本を読むように、女と寝たということでしょうか。
男女が交わることも、日常を構成する総体の一部分で、それだけを特別のこととして取り上げることなどできないと考えるからか、他人にその人の性癖を聴かされても、驚くでもなく、当たり前のこととして村上は聴くことができるのでしょうか。
『嘔吐1979』で語られる男は、村上より2、3歳下のイラストレーターです。本作が書かれた時点で、村上が雑誌に書いた作品にその男がイラストを描いたことがあったそうです。
本短編集は、村上に話をしてくれた人に迷惑が及ばないよう、話の細部を多少アレンジした以外は、大筋は事実と村上は書いています。
そうであれば、当時、村上の作品にイラストを描いた、村上より2、3歳下の男が誰であるか、関係者は見当がつくかもしれません。イラストレーターの数も限られますしね。
その男は、ある特技を持っていました。友人の妻や恋人を片っ端から寝取ってしまうことです。だからといって、友人から妻や恋人を奪うことはしません。ひとときの合いびきを愉しむだけです。
たとえばこんな風にです。
男が友人の家に遊びに行きます。家には友人と妻がいます。友人が近居の酒屋にビールを買いに行ったり、シャワーを浴びている間に、友人の妻と事を済ませてしまうのです。
大胆な話ですが、友人に疑われたことは一度もない、と男は自慢げに話します。
男には何かが決定的に欠けている思わないでもありません。それは、他人の尊厳を守るということかもしれません。しかし、村上がそれらのことを書くことはありません。
男は自分勝手な理屈のようなものを村上に話します。
曰く、女というものはすべからく、異性にかまってもらいたい願望を持つものだ、と。自分は、女の顔を見ただけでそれがわかる。そう思う理由は人それぞれで違うだろう。
ある妻は夫の浮気の意趣返し。別の女は、単なる退屈しのぎ。夫以外の男に相手にされるだけの魅力が自分に残っているか確認する女というのもいる。
こんな話をする男には、決まった恋人はいないそうです。
友人の妻や恋人が、当人の望みで男と関係するのであれば、当人には不満はないでしょう。しかし、その女の夫や恋人には、迷惑千万な男ではありますね。
もっとも、迷惑を受けた男たちが、別のところで、迷惑な男と同じようなことをしていない保証はありませんが。
迷惑な男は、今も現役のイラストレーターとして仕事をしているのでしょうか。
『野球場』で村上に話を聴かせる男の話も、ある意味自分勝手な男です。
銀行員をする男が大学時代の話をします。
当時、男は東京の郊外にある製鉄会社が所有する野球場のすぐそばのアパートに住んでいました。男の部屋は、野球場の三塁側ベンチのすぐ後ろにあり、窓を開けると、目の前に野球場を囲う金網がありました。
男がそのアパートに住むようになった理由が語られます。
球場の外野、センターとライトの中間あたりの後方、川を挟んで見えるアパートの3階に住む同級生の女性の部屋を覗き見するため、男はそのアパートの2階を住居にしたのです。
男は神奈川の小田原出身で、父親が持つカメラと望遠レンズを借りてきて、三脚に据えました。
ファインダー越しに見えるのは、大学のクラブで知り合った同学年の女子学生です。男いわく「かなりの美人」で、近づきたいものの、相手にしてもらえません。
片想いの彼女の生活を徹底的にチェックしてやろうと考えた男は、観察に適したアパートを見つけ、そこから、望遠レンズで女性の生活を覗き見するというわけです。
覗き見をされている女子学生は、部屋が3階だったことや、周りが雑木林や河原のため、まさか自分を覗き見る者などいないだろうと考え、ごく自然に暮らしています。
男は村上に、自分がファインダー越しに見た情景を、ある程度詳細に語っているはずですが、村上はそれらを、文章にしていません。
それを事細かに書くことに、村上は意義を感じなかったせいかもしれません。
書いたのが谷崎潤一郎(1886~1965)あたりであれば、微細に事の始終を書くことに喜びを感じたでしょう(?)が。
カメラに望遠レンズをつけて覗いたと話す男に、村上は「写真はとったの?」と訊きます。
男は答えはこうです。
「写真はとりませんでした。そこまでやると自分がすごく汚なくなっちゃいそうな気がしたんです。もっともただ眺めているだけだってずいぶん汚ないことかもしれないけど、それでもやはり一線は画さなくちゃっていう気がしたんです。だから写真はとりませんでした。ただじっと見ていただけです。(以下、省略)
村上春樹. 回転木馬のデッド・ヒート (講談社文庫) (Kindle の位置No.1712-1715). 講談社. Kindle 版.
とっくに一線を越えておいて、今更、一線を画すも何もないだろうと思わずにはいられません。
男の目に飛び込んできた生の女子学生の実態は「グロテスク」だといい、男は女子学生を避けるため、大学を休んだりします。
勝手に覗き見られて、自分をグロテスクな生体のように思われた女子学生はたまったものではないです。
しかもこれは、村上が頭の中で作り上げた話ではなく、村上が人から聴いた実話ということですから、被害者の女性と加害者の男が、現実の世界にいることになります。
勝手に思い焦がれられて、そのあとに、グロテスクな存在に見られた女性が、自分のことを村上に話され、短編として作品の中に残り続けます。
本作の存在を当人が気がつき、読んで、書かれている女子学生がもしかし自分のことだ、と考えたら、女性はどんな気持ちになるでしょう。
ポイントにつられて読んだ村上作品ですが、読後感はあまりよくないものでした。