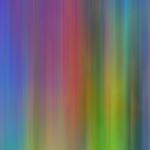義兄(2000年にくも膜下出血で亡くなった姉の夫)に以前から勧められている本があります。中勘助(1885~1965)が書いた『銀の匙』(前編:1910|後編:1915)です。
義兄は、中勘助が自身の幼年と思春期の頃を思い出して書いた自伝小説のような作品で、そこで勘助が自分を「私」として書いた「私」が、私(本文章を書いている私です)と重なるところがある、と事あるごとに匂わします。
私もその小説があることは知っており、電子書籍版をAmazonの端末Kindleにダウンロードしてはあります。が、未だに腰を上げずにいました。
この、勘助の『銀の匙』を取り上げた本で、間接的に作品世界に触れました。
NHKEテレの番組に『100分de名著』という番組があります。私も気になったテーマがあると同番組を見ることがあります。近いところでは、谷崎潤一郎(1886~ 1965)の世界を取り上げた4回の放送は録画しながら見て、本コーナーでも取り上げました。
少し前、谷崎作品に焦点を当てた『100分de名著』の電子書籍版を読んだばかりです。それについては、本コーナーで取り上げることがあるかもしれません。
『銀の匙』の『100de名著』版は、テレビの番組としては放送されていないようです。同番組の別冊という形で、斎藤孝氏(1960~)が講師役となり、2017年10月18日に、東京の筑波大学付属中学校で生徒たちを前に行った特別授業をもとに、のちの加筆も加えて一冊の本にしたものだそうです。
この授業に出席した男女20人の中学生の氏名が記述されています。これらの中学生が3年生であれば、この4月、順調にいった人は、大学1年生になっているでしょう。
本書は4つの章に分けて構成されていますが、私は3番目の章が面白いと感じました。章は講とされ、その第3講の見出しは「生き方の価値観を問い直す」です。
『銀の匙』は幼年時代の前篇と、もっと成長した時代を描いた後篇に分かれているそうです。
幼い頃の「私=勘助」は、男友達と遊ぶことができず、伯母さんに背負われておとなしそうな女の子の傍に連れていかれ、やっとその子と初めて遊ぶ、といった男の子に描かれています。
この様子は、私が幼かった頃に重なります。
勘助が生まれたとき、父は43歳で母が37歳です。
私には7歳上の姉がいましたが、私が生まれたとき、父は40歳、母は37歳になっていました。姉と私の間に姉がもう一人いたはずですが、その姉は死産でした。
母は、私を産んだあと病気がちとなり、私が乳離れする前から入院することが多くなりました。小学生の頃には片目を失明し、中学生のときには全盲となっています。
母が病気がちだったこともあり、私が生まれると、子守の女性が私の家に住むようになりました。歳は姉と近く、私には姉弟のようにその子守を慕っていました。
幼かった私は、子守の女性の自転車の後ろに乗り、遊びに行ったりしていました。
そんな私の幼年時代を知っていた義兄は、『銀の匙』の「私」と私が多分に重なって見えるのでしょう。
斎藤孝氏の特別授業で『銀の匙』の話を聴いた生徒の一人が、後篇では、自分の意見をハッキリいい、先生にも対抗する強い子供として描かれ、まるで別人のようだとの感想を述べたそうです。
その問いに対し、「私」である勘助は、子供の頃から何も変わっていないと解説していきます。
前篇と後篇の「私」は対照的な人物のように見えながら、実は、「意志の強さ」という点では、何も変わっていないと話します。
幼い頃、腕白共に石を投げられても伯母さんの背中にしがみついていたのは、自分の嫌なことに強く抵抗した意思の強さの表れと見ます。
一方、学校へ通うようになった「私」の勘助は、日本が戦争に負けると思えば、周りに忖度して「絶対に勝ちます」とはいわず、「きっと負ける」といって平気な少年となります。
勘助の「私」がこういうのは、意思の強さの表れであり、伯母さんの背中にしがみついて嫌なものを徹底して嫌った幼い彼と、何も変わってはいないというわけです。
『銀の匙』で描かれた時代の日本では、現代の日本以上に、男らしさや女らしさが強要される時代でした。
そんな、今よりも生きにくい時代を象徴する存在が勘助の兄の金一でした。金一は弟の勘助にも男らしく振る舞うことを強いますが、勘助の「私」は兄にちっとも応えません。そのたびに、金一の機嫌が悪くなります。
夜空の星を眺めていた「私」に金一が「なにをぐずぐずしている」と腹を立て、「私」が「お星さまをみていた」というと、金一は「ばか。星といえ」と怒鳴る、といったありさまで描かれます。
特別講師の斎藤氏の授業から離れ、編集に携わった人が書いたのであろう解説でわかることもあります。
勘助と兄との確執については、斎藤氏の授業には登場しません(登場しなかったと思います)。
兄は勘助の14歳年上です。男らしく生きることを求められた時代に順応する兄は、立派に成長し、東京帝大医科を卒業し、子爵の娘である野村末子と結婚します。
単身でドイツに留学して日本に戻った兄は、福岡医科大の教授に就く、といった順風満帆ぶりです。
しかし、人生の行く末はそんな者にも見据えることはできず、医科大の教授に迎えられた4年後、脳溢血を起こし、半身不随となって、言葉を失い、大学を辞職します。勘助25歳のときです。
父母亡きあと、家長の存在であった兄が倒れ、勘助が家を支えなければならない立場に追い込まれますが、意に沿わないものには従うことができない勘助は、家から離脱し、放浪の生活を送ることになります。
その頃に書かれたのが『銀の匙』というわけです。
勘助は、自分に辛くあたる兄を許すような詩を残しています。
世間一般が求める効率の良さや、勝者になるための競争から独り降りて生きる勘助に、私は親しみを持ちます。私もそんな生き方を今の歳まで送ってきているからです。
幼い頃に伯母さんとかけがえのない時間を過ごした勘助は、現実的な損得から離れた世界に生きる幸せを知らず知らずのうちに自分のものにします。
『銀の匙』の後編は、姉様との別れで終わります。この姉様は、兄の金一と結婚した義姉の末子です。
授業の合間に書かれた解説によると、末子は、若くして倒れた夫と中家を支え、理不尽な敵意や虐待に耐えて働いたそうです。頼りにされながらそれに応える生き方ができなかった勘助は、家族や親族から強い非難を受けたでしょう。その勘助を庇ったのが兄嫁の姉様こと末子でした。
末子は、勘助が58歳の年、60歳で亡くなっています。
勘助は末子に恋心を隠し持っていたようです。
特別講師の斎藤孝氏は、話を聴く中学生たちに聴かせる体裁を取りながら、本書を読む人すべてに、「子供らしい驚嘆の眼を常に持ちながら生活してほしい」と要望します。
昨日の続きが今日なのではなく、新しく始まった今日は今日だけのことで、驚きの連続であるはずだ、というわけです。
惰性で生きるのではなく、「はっ!」「はっ!」と驚ける感性を持って、大人になっても子供の頃の心のまま生きてほしい、ということです。
月光に自分の腕をさらし、それまで気づかなかった美しさに気づくこともあります。その時の自分に、地位や名誉は不要です。
文学作品にどれだけ深く浸れるかは、その人がそれまでどのように生きてきたかによって変わります。身体的経験が多い人ほど、深い世界へ降りていくことができます。
デジタルの発達により、身体的経験をしにくくなっている現代は、古典作品の真の理解には難しいといえましょう。
それでも、日々を子供ような感性で生きることができたら、より深く古典作品に親しむことができ、人間性を豊かにすることができるでしょう。
近いうちに『銀の匙』の本編に接してみたいと考えていますが、そのときは、斎藤氏が本書で講義してくれた内容を一旦忘れ、自分の感性だけで接することにします。
「100分de名著」から別冊の『私たちの手塚治虫』が電子書籍版で出ていることを知り、こちらも入手して読み始めたところです。これも読み終わったら、本コーナーで取り上げることになるかもしれません。
なお、こちらは50%オフのキャンペーン対象本には含まれていません。